TOP
> 組合について
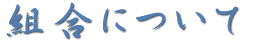
■沿革
昭和16年、物価統制令によって12名の組合員により滋賀県漬物工業組合を設立。会長に辻川治三郎氏が就任。その後昭和23年3月に発展的に解消し、新しく31名の会員増強をもって滋賀県漬物協会(会長・辻川治三郎氏)が設立された。昭和46年に、任意団体から、全国的な動きでもあった法人化へ移行するにあたって、滋賀県漬物産業協同組合と滋賀県漬物第一協同組合に分かれた。その後、連合会として、対外的な活動を続けると共に本来の一本化を目ざすため、徐々に整備を進め、滋賀県漬物第一組合を解散、同組合員が滋賀県漬物産業協同組合に加入する。その後本県業界組合として相応しい名称、滋賀県漬物協同組合に変更する。名称変更の知事認可を受け、平成8年11月11日に登記を完了し、現在に至っている。
■現況
組合員の大半がメーカーとして滋賀県特産品の製造あるいは卸を営んでいる。近年は京阪地区のベッドタウン化に加え、核家族化等で宅地化が急増、全国でもトップクラスの人口増加県となっている。そのため、卸業についても県内の卸売市場の整備等により充実が図られている。地域特産の日野菜あるいは紅かぶといった伝統的な漬物加工は勿論、近年の消費者嗜好に沿った調味浅漬の製造においても、組合員各社それぞれの技術を活かし、原料野菜の安定確保を追求しながら全国へ出荷を続けている。特に原料野菜や製造技術に関しては、組合活動の一環として情報交換や見学等実施し、積極的な組合活動を行っている。
昨今は滋賀県の「ものづくりフェアー」(県民の皆様‐特に幼少の時期‐に「ものづくりの楽しさ」や「ものづくりの素晴らしさ」を体験してもらう機会を設け、広く「ものづくり」をアピールするとともに、県内企業に働く技術労働者や職業能力開発施設訓練生等の技能競技大会を開催することや、高度熟練技能者やおうみの名工による実演等により、ものづくり産業の基幹となる技術・技能取得意識および技能尊重気運の高揚を図り、本県産業の発展に寄与することを目的に開催されている)
などにも参加をし、近江つけものの啓発活動にも力を入れている。
|