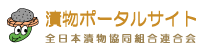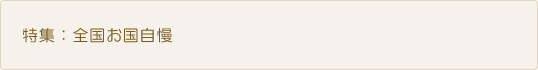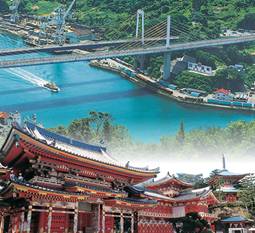���������@�L��[�S�������������ꂱ��]

[�L�����́u���{�̏k�}�v]
�L�����́A�����n���̒����t�ߓ쑤�Ɉʒu���A���T���[���X�A�k�A�t���J�̃����b�R�k���Ƃقړ����ܓx(�k�܂R�S�x)�B�ʐς͖�8�C480���u�ŁA�S����2�C2���A�����n����26�C6�����߁A�s���{���ʂł́A��������(��9�C044���u)�Ɏ����S��10�Ԗڂ̑傫���ł��B
�n�`�I�ȍő�̓����́A�W��1�C000�����̒����R�n�����f���錧�k������A�������ɂ͐�����n�Ȃǂ��ʒu���A�암�ɂ͐��˓��C�ɖʂ���͌��t�߂ɔ��B�����f���^�i�O�p�B�j�𒆐S�Ƃ����A���፷�ɕx��3�i�̊K�i��ƂȂ��Ă��邱�Ƃł��B�����������፷�̂���n�`�ɂ��A�R�ԕ��ł͊��f�w��Z�H��p�ɂ���Đ��ݏo���ꂽ�O�i�����ߋ��Ȃǂ̗D�ꂽ�i�ς����ݏo����Ă��܂��B������ݕ��ł́A���˓��C�ɕ����ԑ召�����̓��X����������D��Ȃ��Ă��܂��B
�암�̋C��́A�k�ɒ����R�n�A��Ɏl���R�n�ɂ͂��܂ꂽ�n�`�ɂ��A�G�ߕ��̉e�����ɂ����A�~�J�ʁA�~��ʂƂ��ɏ��Ȃ��A���V�������Ƃ��������������˓��C���C��ƂȂ��Ă��܂��B����A�k���́A���{�C������̎�������C���R�n����邽�ߓ~�G�̍~��ʂ������Ȃ��Ă���A�����ő��ʓI�ȋC��������Ă��܂��B
�N���ϋC���́A�암�ł́A�L���s�Ǝ��Ӓn���16�����x�Ɖ��g�ł��B�k���ł́A�k�����͉��ݕ�����5���Ⴍ�Ȃ��Ă���A�����s���쒬�̔N���ϋC���͐X�s�Ɠ�������11�����x�ł��B�~���ʂ́A���k�����̔����i2�C400�o���x�j���ł������Ȃ��Ă��܂��B����A�암�͍~���ʂ����Ȃ��A���Ɍ��쓌���̈����Ȃǂł�1�C200�o���x�Ɣ����̖��ł��B
���̂悤�ɍL�����́A���l�Ȓn����C��������Ă��邱�Ƃ���A�Ⴆ�A���g�Ȑ��˓��C���݂ł̓~�J���̐��Y������ł���A����Ȍ��k���ɂ̓����S���Y�n�т�����܂��B�܂��A�X�|�[�c�ʂł́A���˓��C���݂Ⓡ�Ƃ����͊C�����̃��b�J�Ƃ��ē��킢�A�R�ԕ��͖{�B�œ�[�̖{�i�I�ȃX�L�[��G���A�Ƃ��ėL���ł��B���̂悤�ȕ��y�́A�L�������u���{�̏k�}�v�Ƃ������鏊�ȂƂȂ��Ă��܂��B
[�s���h�Ȍ�����]
��ʓI�ɍL�����̌������́A�u�V�������̂��������C�������s���h�v�Ƃ�������ŁA�u�M���₷����߂₷���v�Ƃ������܂��B�s���h�̗�Ƃ��āA��������ȍ~�̊C�O�ږ����̑����i�S����j���������܂��B
�o�g���ʂ̊C�O�ږ��� |
|||
���� |
�s���{�� |
�ږ��� |
�V�F�A |
1 |
�L���� |
98,975 |
13.6% |
2 |
���ꌧ |
79,454 |
10.9% |
3 |
�F�{�� |
72,699 |
10.0% |
4 |
������ |
55,776 |
7.7% |
5 |
�R���� |
47,430 |
6.5% |
�S�@�@���@�@�v |
728,696 |
100.0% |
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�����F�L�����j
�܂��A�����͍]�ˎ���Ɂu���|�n���v�Ɓu����n���v�ɔ˂�������Ă������ƂȂǂɂ��A�n��ɂ���ē���������ƌ����Ă��܂��B
�s���|�n���̓����t
�]�ˎ���A�L���˂͖��{�Ƌ�����u����������Ƃ��Ă������Ƃ���A�������y�ӎ�����܂�܂����B�����ȍ~�́A�R�����_�Ƃ��Đ�[�Z�p���W�ς������Ƃ���A�����ԃ��[�J�[�͂��ߗl�X�ȍL�����̑S����Ƃ��炿���Ə鉺���I�ȎY�ƍ\�������ݏo����܂����B�܂��A�L���s�͈��K�͂̎s��K�͂�W���I�ȏ��������Ȃǂ���A�É��s�ƕ���Ńe�X�g�}�[�P�e�B���O�ɓK�����y�n���Ƃ����܂��B�É��s�����ϓI�ȏ��i�̔������݂�̂ɓK���Ă���Ƃ����̂ɑ��A�L���s�́A��i�I�ȏ��i���e�X�g����̂ɑ��������Ƃ����Ă��܂��B
�s����n���̓����t
�@�]�ˎ���A���R�˂͍L���˂Ɣ�ׂĖ��{�Ɛ[���W�ł��������߁A�]�˂̕������������������ꂽ�i��̋C���̕x�ޔ���l�C������܂�܂����B�����ȍ~�́A���|�n���Ƃ͈قȂ�A�R�����Ȃ��������Ƃ���A��Ə鉺�����`������悤�ȎY�Ƃ͈炿�܂���ł����B�������������u���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ����Ɨ����_��|���A����I�Ȑ��i��V�����r�W�l�X��n������I�����[������Ƃ𐔑������݂܂����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�Ђ났��o�ό������@�u�J�����g�Ђ낵�܁v��蔲���j
[�L�����̖��́u��̐��E������Y�Ə���ӂ�钬���݁v]
���E������Y�@���̈�@�w�{���E�����_�Ёx
�����������A�������ɂ���đ��c���ꂽ�Q�a����̚����_�Ђ̎Гa�ƊC�ɂ��т�����h��̑咹�����쌱���炽���Ȗ�R�i�݂���j��w�i�ɂ��āA�D���Ȑ��E��D�萬���Ă��܂��B���E������Y�ɓo�^���ꂽ�����_�Ђ₻�̎��ӂ�����A���Â���C�̎��_�Ƃ��Đ��q����Ă������R�╶�������炽�߂Đ[���m�邱�Ƃ��ł��邱�Ƃł��傤�B |
 |
���E������Y�@���̓�@�w�����h�[���x
1915�i�吳4�j�N�Ƀ`�F�R�̌��z�ƃ����E���c�����̐v�ōL�������Y��قƂ��ĊJ�ق��A���̌�L�����Y�Ə���قɉ��̂���܂����B�h�[���^�̉�����A�[���̕ǂ������ꂽ�����̑��肪��ۓI�ł����B 1945�i���a20�j�N8��6���Ɍ������������A ���S�n���ӂ̌��z���͂قƂ�Ǖ��܂������A�قڐ^�ォ�甚���������Ƃ���K����ő����������肾�������߁A���̌����͑S���Ƃ�܂����B���ꗎ�����O�ǂ�ނ��o���ɂȂ����S���������̎S�����A���̎p�͍P�v���a�̃V���{���u�����h�[���v�Ƃ��āA���E�Ɍ����ĕ��a�̑����i���Ă��܂��B1996�i����8�j�N12���ɐ��E������Y�Ƃ��ēo�^����܂����B |
|
�f��䂩��̒��Ƃ��Ă��m����A�������ۂ̉Y�B
�Â�������H�n�A�Â��Ȓ�������̕��i�ȂǁA�^�C���g���b�v�����悤�ȉ����������y���݂Ȃ���A�������U�I�X�X���B��������͂��߂Ƃ����Î��߂���̌�ɎR�������i�����n�������A���҂��`�Ƃ��ĉh�����ۂ̉Y�A���ǂ̌����ɏh�꒬�̖ʉe���c���㉺�ȂǁA�S���ق�킩������m�X�^���W�A���y����ŁB |
|
[�L�����̐H����]
�@�L�����ɂ́A���y��K���Ȃǂ̉e�����A���D�ݏĂ�����݂��\���ȂǑS���u�����h�ƂȂ��Ă�����̂̑��A�ŋ߂ɂȂ��Ē��ڂ��n�߂����̂ȂǁA�e�n�ɒn��Ɠ��̐H���������W���Ă��葽��ɘj���Ă��܂��B
�����D�ݏĂ� ��H�̕Ă��s���������Ɏq���̂����������K�m�H�����ɖ�Ȃǂ𑝂₵�����̂����D�ݏĂ��̎n�܂�B�ߔN�ł́u�����n�O�����̑�\�i�v�Ƃ������A���D�ݏĂ��X�͍L���s������800���ȏ�A�����ł�2�C000���߂�����ƌ�����B |
 |
 |
�����݂��\�� ���݂��̖����Ƃ��Ēm������{�O�i�E���|�̋{���̖����ŗL���ŁA��\�I�ȓy�Y�i�B���\���̈��ŁA�������E���E�����E�I���������傤�Ƃ���J�X�e����̐��n���Q���݁A���~�W�̗t�������ǂ����^�ɓ���ďĂ��グ��B�Q�́u��������v����{�ł��邪�ߔN�ł́u�`�[�Y�v�A�u�N���[���v�A�u�����v�ȂǑ����̃o���G�[�V����������B |
���L���ؒ� ���{�O��ؒЂ̖��O�ɑ��������A�L���ȕ����ƒ��ǂ����ꂩ��L���ł́u�Ђ��̉��l�v�Ƃ�������B |
 |
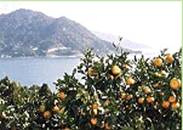 |
������ ���˓��̓��X�͂��ނ̕�ɁB ���Y��������͂������̔��˒n�ł���A�������̐��Y�͓��{��ł��B |
�����R�� ��������퍑����ɂ����Ĉ�����{���n�Ƃ������㐅�R���A�K���F��Ǝm�C���g�̂��߁A�o�w����ۂɐH�ׂ��Ƃ����痿���B����ނƊC���������Ղ����A���z�Ȃǂ��g�����o�`�Ŏύ��ށB�u�����̓G���v�Ƃ����Ӗ��Ń^�R�͕K�����ꂽ�Ɠ`������B |
 |
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�L�����ό��z�[���y�[�W���@�����j